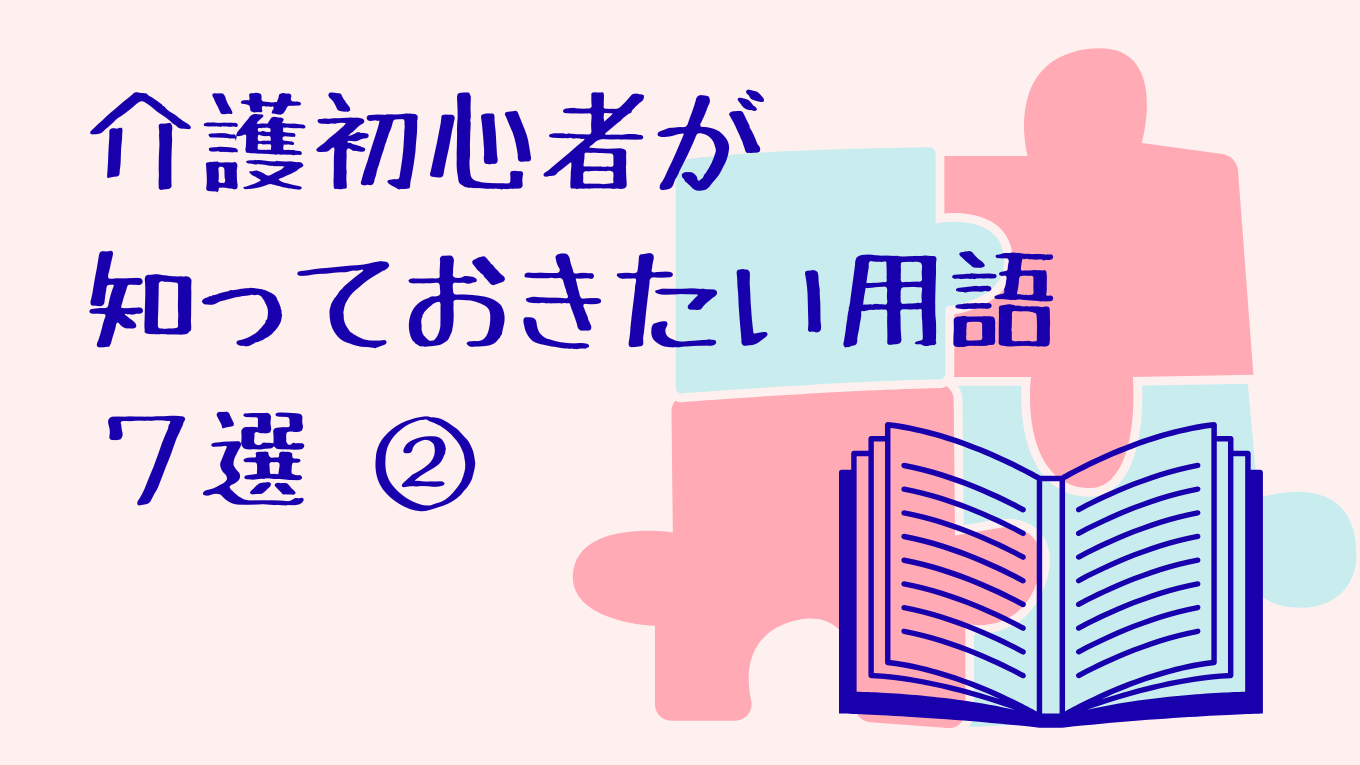介護初心者がまず知っておきたい用語7選①【現役ナースがやさしく解説】
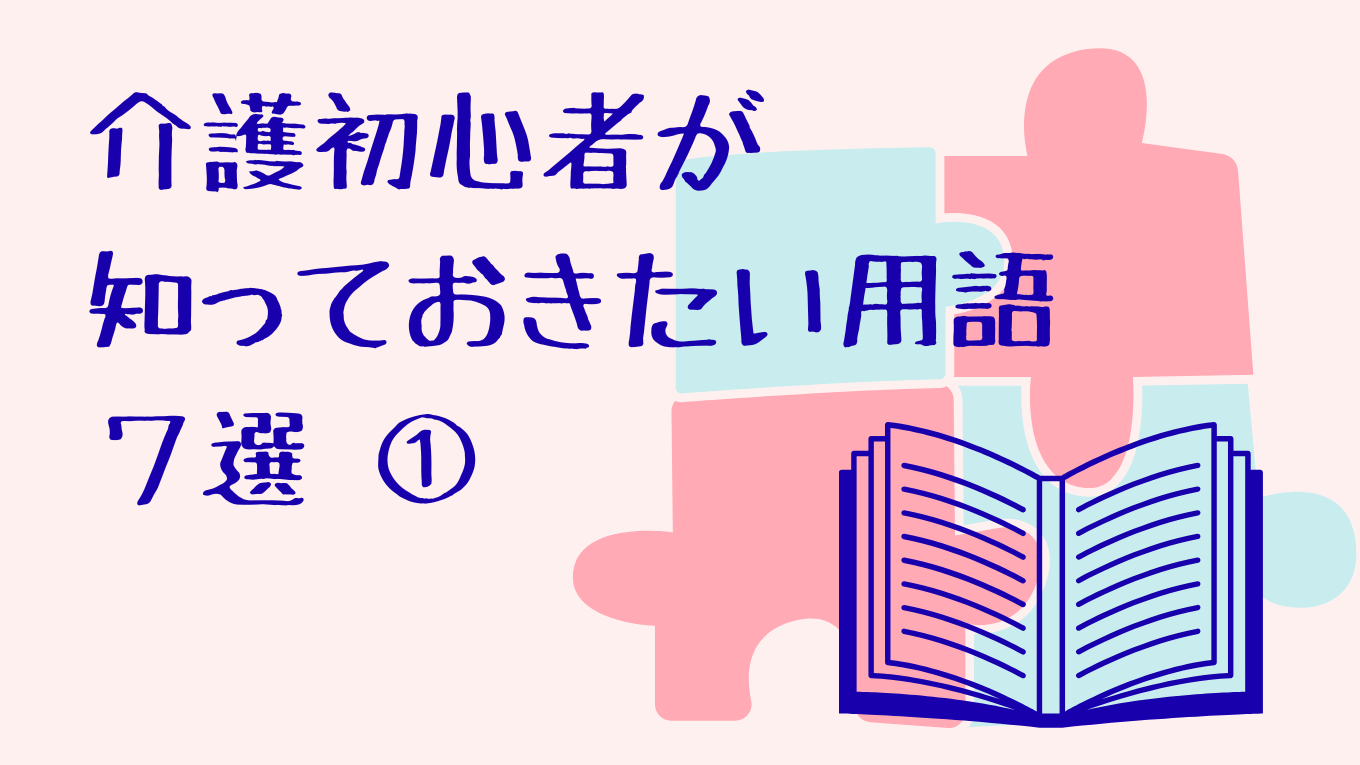

デイサービスってどうやったら利用できるんだろう?

まず要介護認定を受けて、要支援か要介護か判定してもらうの。

ヨウシエン?ヨウカイゴ?聞いたことない言葉だな。

そう、聞きなれない言葉がたくさんあるから、私も勉強中なの。
初めての介護に直面すると、知らない言葉ばかりで戸惑っていませんか?
「要介護って何?」「ケアマネ?」「バイタル…?」
一つ一つの言葉を知っておくだけで、介護の全体像が見えやすくなり、不安はぐっと軽くなるでしょう。
この記事では、在宅介護を始める前に知っておくと安心な7つの基本用語を、現役ナースの視点からやさしく解説します。
介護初心者が知っておくべき用語7選
1. 要介護/要支援(ようかいご/ようしえん)
「その人の生活にどれくらいの介護サポートが必要か」を段階的に示したもの
- 「見守りだけで大丈夫」から「食事や排泄も手伝いが必要」まで、サポートの量を数字で表している
- 要支援1、2・要介護1〜5の7段階で、要介護5が最も重度
この認定結果によって利用できるサービスの種類や回数が決まります。
介護認定調査を受け、結果が出るまでには約1ヶ月かかります。利用したいと思ったその時に、すぐに手続きを始めましょう。

私も最初は「要介護3」とか数字で言われても最初はチンプンカンプンでした(笑)。数字は冷たい印象だけど、“サポート量の目安”と考えればちょっと理解しやすくなりますよ。
2. ケアマネージャー(介護支援専門員)
介護サービスを一緒に選んで調整してくれる「介護のコーディネーター」
- 病院の主治医のように、在宅介護ではケアマネが中心になって支援を組み立てる
- サービスの種類や頻度、費用のことまでトータルで相談できる
家族だけで抱え込まず、まずケアマネに相談するのが安心につながります。

ケアマネさんは、介護の世界のナビゲーター。いいケアマネに出会えると、介護は半分くらいラクになります。「このケアマネさんとは合わないな」と思えば変えることもできるんですよ。
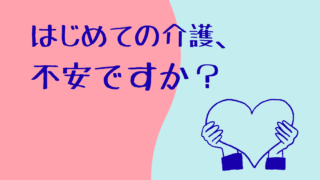
3. ADL(エーディーエル:日常生活動作)
食べる・着替える・トイレ・入浴など、毎日の基本的な動作のこと
- 「どのくらい自分でできるか」が介護の必要度を把握する目安になる
- ADLは「生活の基礎体力」を表すもの
変化を見逃さないことが、早めのサポートや適切な介護につながります。

ADLが落ちてくると介護度が上がる。難しい話に聞こえるけど、つまり生活の基礎体力を表してると思えばOK。
4. IADL(アイエーディーエル:手段的日常生活動作)
買い物・掃除・電話・お金の管理など、少し応用的な生活動作
ADLが「基本動作」だとすれば、IADLは「暮らしを続けるためのスキル」と考えると、わかりやすいでしょう。

買い物の計算がちょっと怪しい、掃除をしなくなったなどもIADL低下のサイン。実は家族が一番気づきやすい変化なんです。
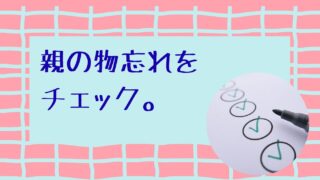
5. バイタルサイン(体温・血圧・脈拍など)
体調の変化を示す「体の信号機」のようなもの
- 体温・血圧・脈拍・呼吸数などの総称。
「体の元気度」を数字でチェックすることができます。病院でもよく聞きますね。

見た目が元気でも熱があったり、血圧が上がっていることがあります。数字はうそをつかない。だからこそバイタルサインのチェックは大事なんです。
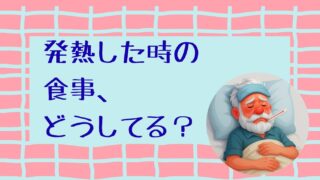
6. 嚥下(えんげ:飲み込み)
食べ物や飲み物を飲み込む動作のこと
- 「安全に食べることができるかどうか」を左右する重要な機能
- 嚥下が弱まると誤嚥性肺炎などのリスクが高まる

「むせ込み=老化」じゃなくて「嚥下のSOS」です。気づいたときに対応すれば、肺炎を防げることも多いんですよ。
7. レスパイトケア(家族の休息支援)
介護をしている家族が休息を取るための支援
ショートステイやデイサービスの利用も含まれ、「休むことも介護の一部」と考える大切な視点です。

私が休んだら親がかわいそう、って思いがち。でも、休まないと倒れるのは介護してる人の方。レスパイトは罪悪感じゃなくて戦略です。
意味がわかると安心
介護の専門用語は難しく感じますが、意味を知るだけで「介護の地図」がぐっと見えやすくなります。
今回紹介した7つの用語は、在宅介護を始めるときにまず理解しておきたい基本セットです。
制度を知り、体調を見極め、家族も休む。その土台ができれば、介護はぐっと安心して進められます。
これから介護が始まる方、すでに向き合っている方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。

介護の用語集、引き続き書いていきますね。